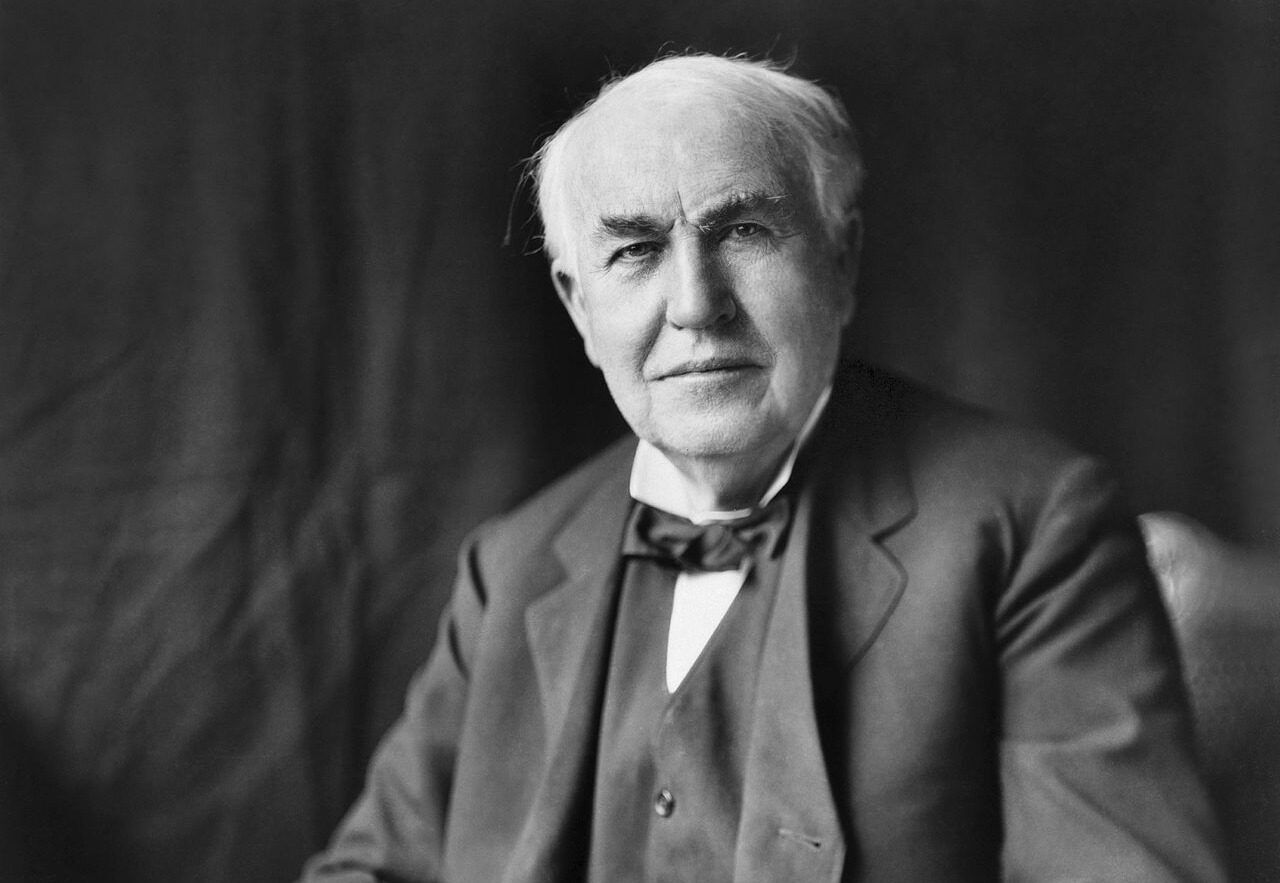民俗学のどなたかが書いていたことなのですけど、巫女であるとか、
卜占を仕事とされている人たちの原型というのは「河原者」と呼ばれていたような存在だったそうです。あるいは芸能に関わる仕事というのも同じように呼ばれていたそうです。
ヨーロッパであれば、ヒターノ(昔はジプシーと呼ばれていましたけど)が生業としていたような職業ですけど、彼らは中間領域を生きているということになっていました。
川のこちら側、つまり此岸は生きている人間の領分ですね。そして、三途の川に表されるように、死後の世界というのは川の向こう側、つまり彼岸にある。此岸と彼岸の間にある河原で活動していた者が「河原者」と呼ばれたそうなのですけど、彼らは中間領域を生きていた訳です。
今でも芸能に携わる方たちを揶揄する「河原乞食」という言葉が残っているそうですけど、それは「どっちつかず」ということですね。生きている者と亡くなっている者の中間の者なのですから。
ジェーン・バーキンが体現していた「どっちつかず」というのは、そもそもフランスで活躍していましたけど、イギリス人という出自からしても運命付けられていたように思うのです。
アニエス・ヴァルダのカメラの前で、ジャンヌ・ダルクを演じてみたいけれど、こんなイギリス訛りのフランス語じゃ観客に笑われてしまわねと自分を評するシーンがあるのですけど、それがきっとジェーンの魅力なのでしょう。
そもそもジャンヌ・ダルクが戦ったのは100年戦争時のイギリスだった訳ですから、イギリス訛りのフランス語というのは、ジャンヌ・ダルクを演じるのであれば、奇妙なねじれを引き寄せてしまうでしょう。
本人の意思とは裏腹に、願いが常に奇妙にねじれて叶ってしまう。そういう才能を持った女性として、ジェーン・バーキンは記憶されることになるのかもしれません。
娘を亡くした後、うつ病と心臓病で苦しみながらも、一人で自立して生きることを決めた翌日に亡くなったそうですから、彼女の願いは最後までねじれて叶い続けてしまったのだと思うのです。