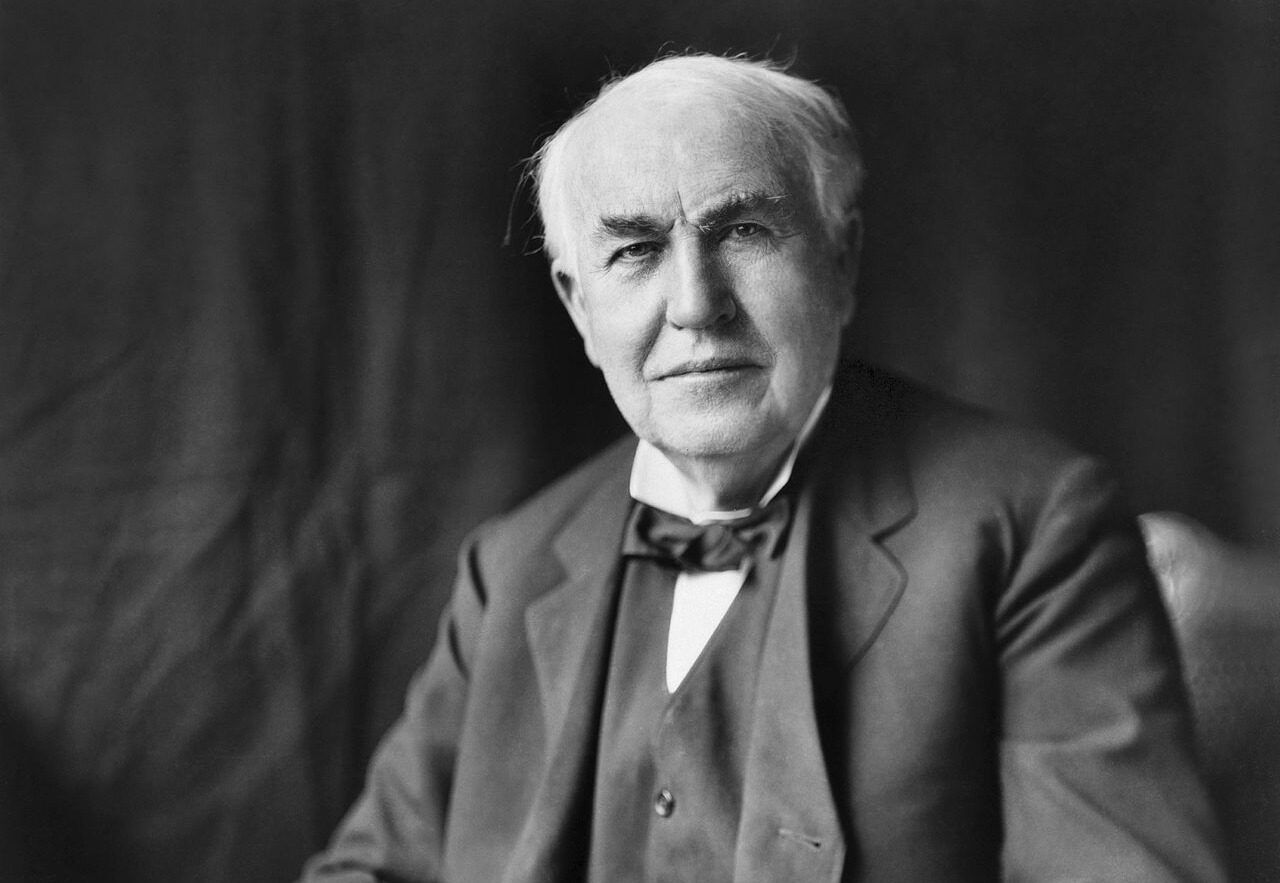妻輝子を演じた音無美紀子さんはハマり役ですね。彼女の存在そのものが、舞台を喜劇的にねじ伏せるような役割をしている。悲しい話にしようと思ったら、いくらでもできるのでしょうけど、彼女の持っている、どんな自分でも、どんな夫でも、どんな状況でも肯定するという、ある種の強さが、どうあがいても舞台を明るくしてしまうのです。
弟子が茂吉の歌の草稿を読んで、え、先生はどうしてしまったんだという顔をしている時。それは悲劇なのですけど、そんなことは私には関係がないと言わんばかりの輝子の、もう一つの中心が舞台全体が悲劇に陥ることを止めてしまうのです。
気になったのは、船医としてヨーロッパに向かった次男がどうなったかということです。本当に舞台にのめり込んでいた私としては…もう気分は親戚のおばさんですよね。あの子はかなり船酔いしていたみたいだけど、無事に戻ってこれたのだろうか、茂吉に再会できたのだろうか。そんなことが気になって仕方なくなったのですね。
それで帰宅してすぐにWikipediaで調べたのですけど…彼はその後の北杜夫さんだったのです。彼の夢は叶ったのですね。まぁ、そんなことを知らないのは、私だけなのかもしれないですけど。
もう生まれて初めての経験なのですけど、私はWikipediaを読みながら泣いてしまったのです。それはまぁそうですよね。Wikipediaを読んで泣いたなんて話は聞いたことがないですから。私を心配性の親戚のおばさんにしてしまったのですから、それだけ引き込まれていたのでしょうね。
そうか、『どくとるマンボウ航海記』というのは、あの旅のドキュメントだったのか。これは是非読まなければと思いましたね。
タイトルの『つきかげ』とは、茂吉の晩年の歌集のタイトルなのだそうです。舞台でも、鰻でも食べましょうかという妻の言葉に、油が濃くて食べられないと答えるシーンがあるのですけど(それで、ドジョウなら食えると言うのですけどね)『つきかげ』にはこんな歌がありました。
「ひと老いて 何のいのりぞ 鰻すら あぶら濃過ぐと 言はむとぞする」
きっと鰻が好きだったのでしょう。鰻の歌は他にもあります。
「戦中の 鰻のかんづめ 残れるが さびて居りけり 見つつ悲しき」
この悲劇とも喜劇とも言えないような悲しさ。それが舞台『つきかげ』の味わいでもあると思います。