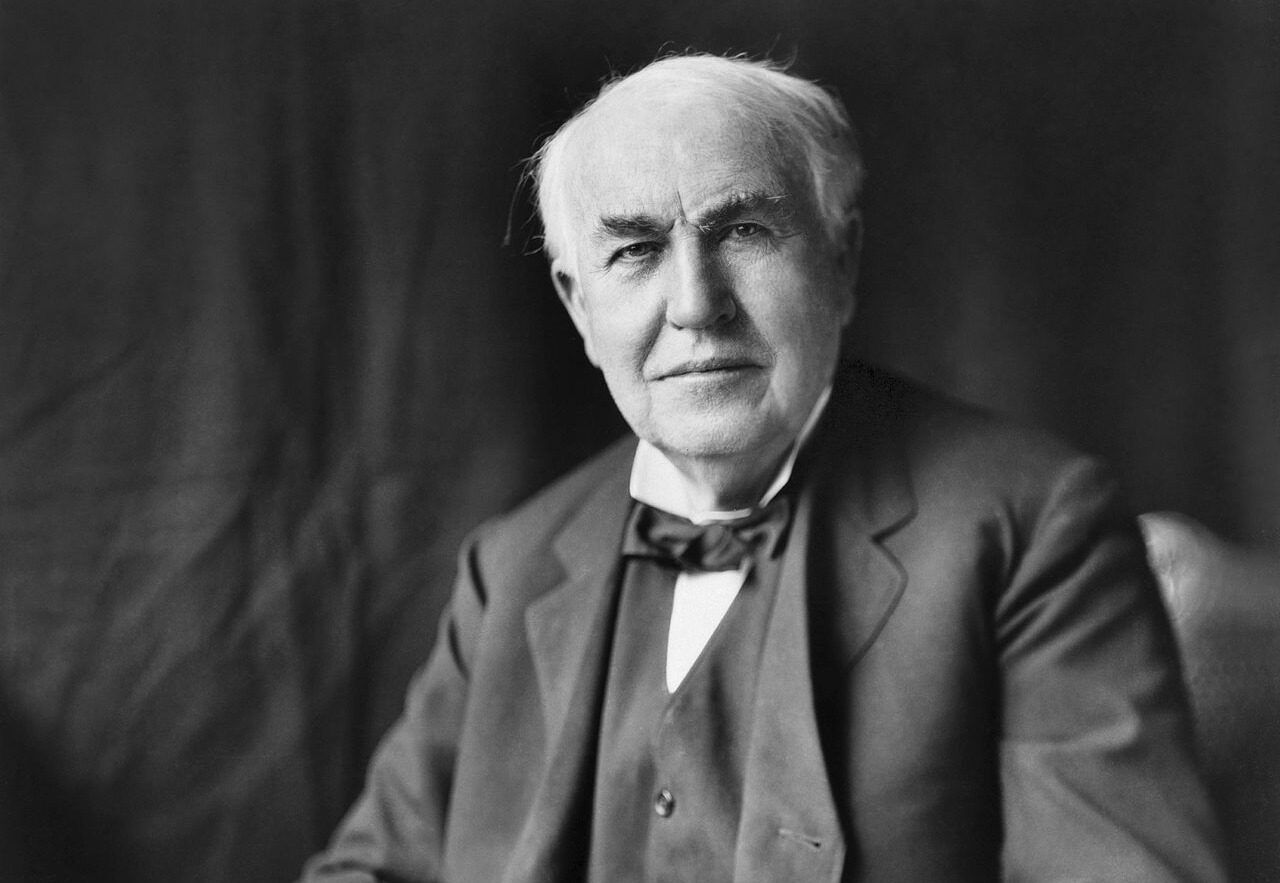「「宿神=シャグジ」的な超空間と現実の世界は、
薄い膜のようなもので隔てられていて、
二つの異質な領域が教会をなくしてしまうことは起こらない。
そのかわり、この境界線のところでは、たえまなく「転換」の過程が繰り広げられている。
そのおかげで、現実の世界は計算のできないもの、
予測のできないこと、現実の枠をはみ出していく過剰したもの、
要するに生命と意識の源泉からの力を、受け取ることができるのである。」
中沢新一は『精霊の王』にこう書いているのですけど、
『やってくる』で郡司ぺギオ幸夫が懸命に説明を試みているのは、
つまりこのような「外部」のことなのだと思うのです。
郡司ぺギオ幸夫は、自分が経験したある種の離人症のような体験について語るのですけど、
かなり怖いです。彼はそれを「いま・ここが凍りつく」と表現するのですけど、
学生時代に研究会の打ち上げをしているときに起こったことだそうです。
現実からリアリティが失われていく。
その時には何かパチンと弾けるような、留め金が外れたような感覚があったそうです。
目の前の景色が遠のいたような感じ、風景が色褪せた感じになって、リアリティを失った。
彼はそう書いています。
声が出ない、視覚・聴覚などで構成される
世界像の変化(それには恐怖という感情が伴います)の後、
目の前にモニターのようなものが現れ、断片的に聞こえてくる言葉や、
何か言おうと思って頭に浮かんだ言葉について、
それがどのような意味で使われるのかの一覧のようなものが羅列され始めたそうです。
これは、離人症の患者さんが語る世界とよく似ています。
「「いや、ビールはいらないです」と言おうとすると、ビールだけではなく、
「いや」「いらない」「です」といった言葉一つひとつに対して意味の列挙が始まり、
自分がどのような意味を選択し、文全体として何を言おうとしているかわからなくなる」
モニター画面は一面で停止することはなく、肉眼で画面を追うことが不可能なスピードで動いていく。列挙されるそれぞれの意味がなぜか全て理解できている、という全能感が自分にはあった。
著者はそう書いているのですけど、
彼はこの状況を「外部に接することなく言葉の世界に封じ込められ、
その内部を循環してしまった」と表現します。
現実のリアリティを支えているのは、きっと言語化される以前の何か過剰なもの。
彼はそのことに思い至るのです。