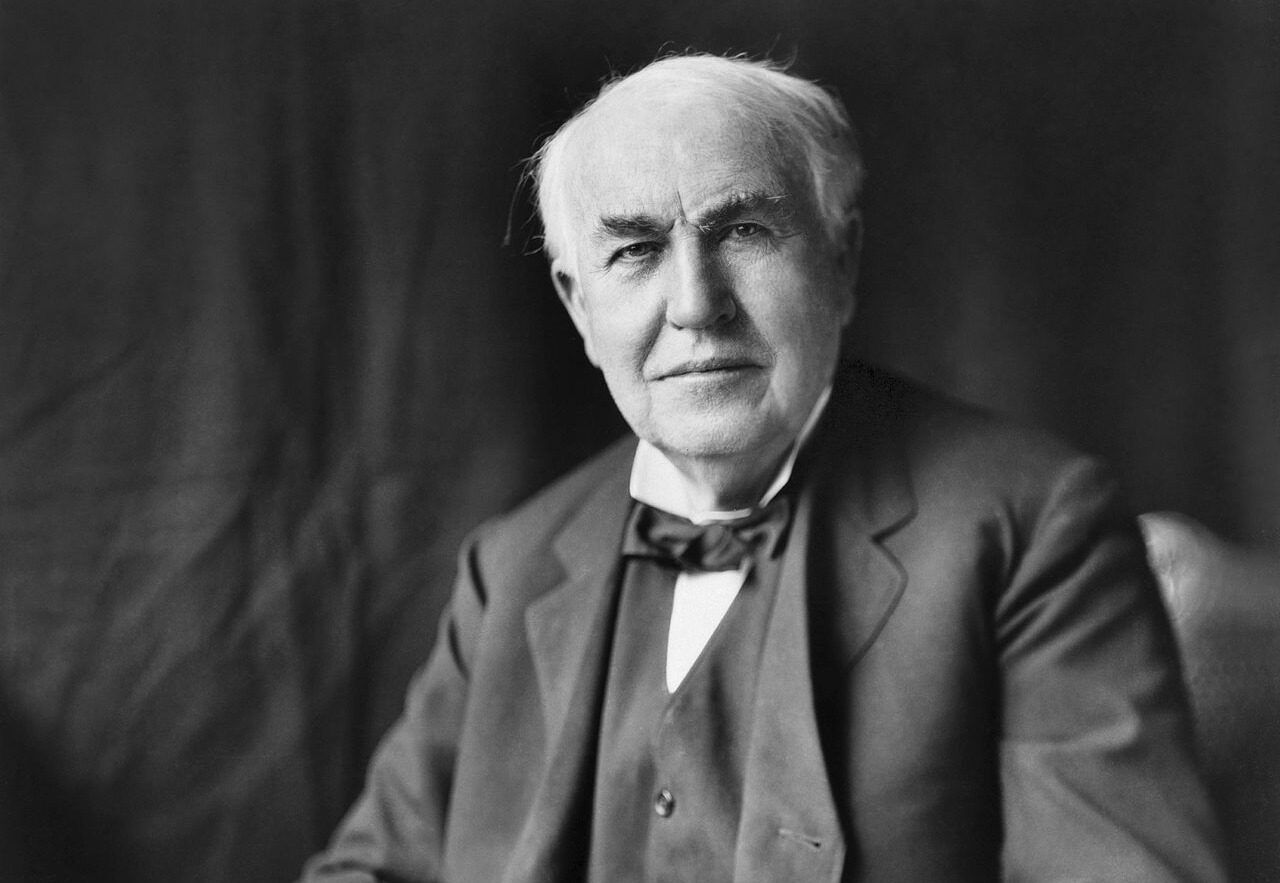アメリカ先住民の研究を通じて、フランツ・ボアズがたどり着いた概念(正確には、彼の門下生だったメルヴィル・ハースコヴィッツの言葉です)が「文化相対主義」です。
レヴィ=ストロースと同じように、文化には優劣の差がないという考え方ですね。
ボアズ派は、文化というのは「生のあり方」だと考えました。ways of life と書いた方が感覚的に分かってもらえるかもしれません。朝食がパンとコーヒーであっても、味噌汁とご飯であっても、お粥と揚げパンだったとしても、それぞれの文化は相対的なものにすぎず、優劣はないのです。
「文化に優劣はない」のように…私たちが今では当たり前のように考えているけれど、昔はそうではなかった考え方。人類学の歴史の中でそれが形作られていったと思うと、なんだか人間という存在を尊敬できるような気がしてきます。
私はここまで研究した。あとをお願いします。あとを継いだ誰かはさらに研究をする。そしてまたその先を誰かに託す。どんな学問もそうでしょうけど、そうやって発展してきたのですよね。私もフロイトから始まった精神分析の、枝分かれしまくった道の先っちょにいるわけですし。
『はじめての人類学』は最重要人物の最後に1人。ティム・インゴルドと共に締め括られていきます。「人類学者は世界の中で哲学する。人類学者は彼らが対象として選んだ人々とともに研究する…とりわけ、観察、会話および参与実践に深く巻き込まれることを通じて。」
インゴルドは『人類学とは何か』でそう言っています。つまり自分たちの文化の外部で暮らす人々に「ついて」語ることではなく、現地の人々「とともに」人間の生に継いて学ぶことが人類学なのだと、インゴルドは定義しているのです。
現地の人々と共に暮らしながら、研究する余白にプライベートな日記を書く。
マリノフスキは日記をなぜ書くかについて「仕事同様人生に対しても深みを加えるという目的のため」と書いていましたが、その言葉は人類学の歴史の中に生き続け、最先端にいるインゴルドの言葉の中に反響しています。
人類学のにわかファンになった私の中にも…ですね。インゴルドの本を読まなくちゃ。