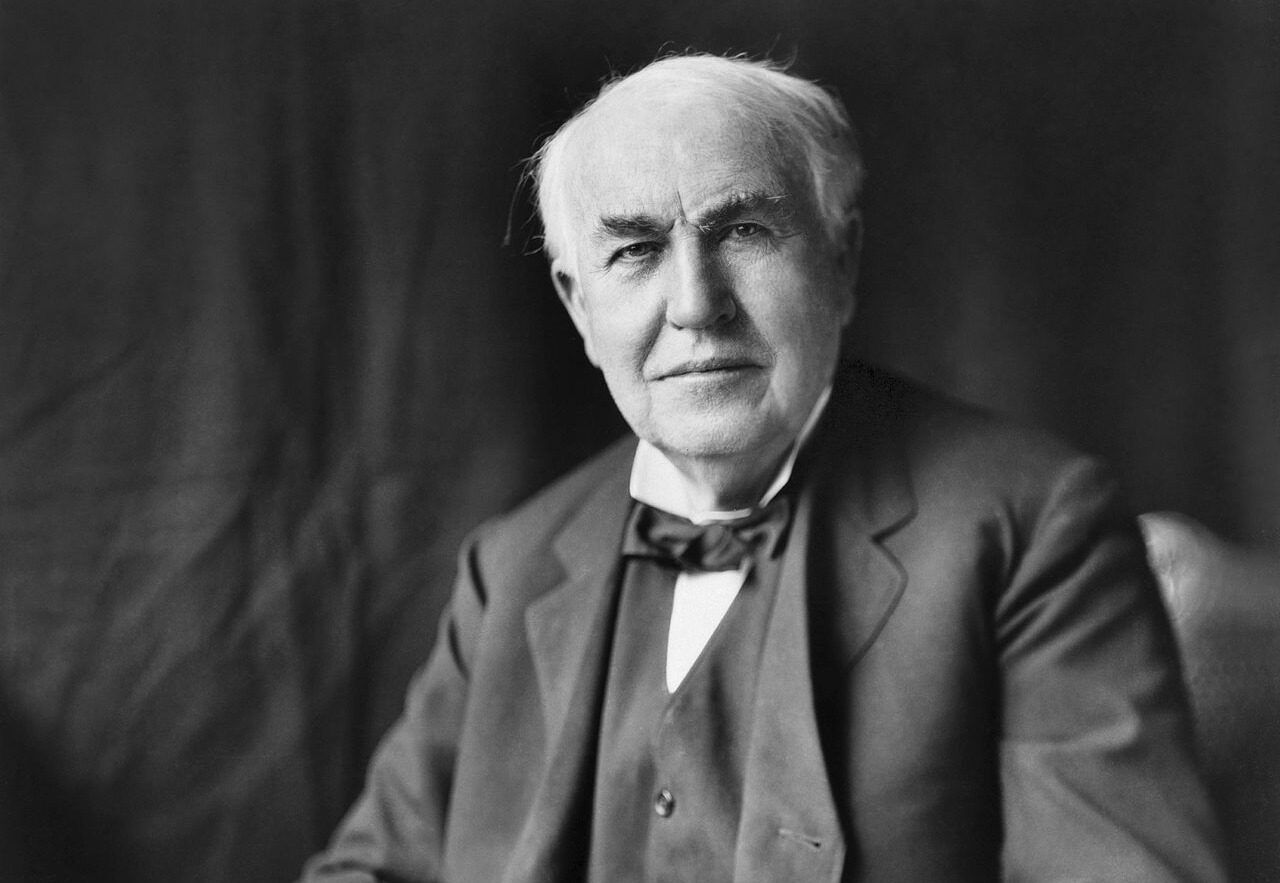新しいル・シネマにはもう何度も来ていて、先日も『阿賀に生きる』と『阿賀の記憶』を見たのですけど、なかなかに座り心地のいいシートだし、前の席との間隔もいい感じで、好きなのですよね。売店のコカ・コーラが瓶入りなのも好みなのです。
午後1番の回で『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』を見たのですけど、これはもうサングラスをかけないと(日差しが強かったので持ってきてよかった)外に出られないのではないかと思うくらい泣いてしまいました。
涙がたくさん出たから名画だと言うつもりはないのですけど、むしろ泣かせようという演出がされていないことが、この映画を奥ゆかしいものにしているのですよね。だけど涙は溢れてくる。
好むと好まざるとに関わらず、エモーショナル・コントロールが映画制作に持ち込まれた世界に私たちは生きている訳です。よし、ここら辺で観客の感情が盛り上がるから泣かせどころだなとか、そういう計算が巧みにされているということです。
それが悪いこととは思いませんけど(高倉健さんの任侠映画だって、健さんがこらえて、こらえて、最後に怒りを爆発させるという構造になっていますからね。)何だか誘導されているなぁと感じることは、個人的にはあまり好みじゃないのですよね。
ナチスドイツが、オーストリアとズデーデン地方を併合した1938年から、ポーランド侵攻の1939年9月1日までの間に、669人の子どもたちをイギリスに避難させたニコラス・ウィントンの実話なのですけど、それが本当に起こったことというだけで、もう私は泣けてきてしまうのですよね。