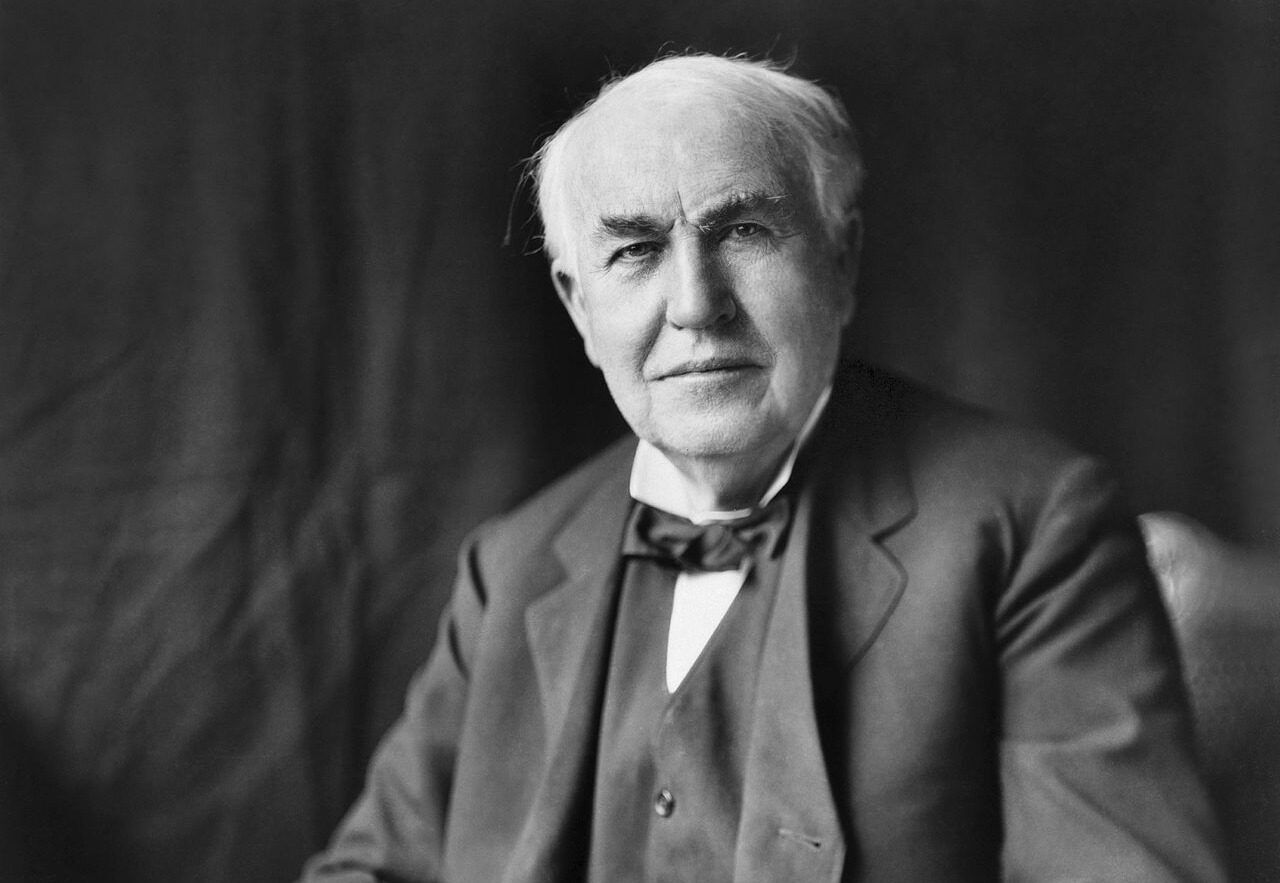映画の中で対比的に扱われるのが、村と都会です。
もちろん小作人として搾取されているのですけど、明るい太陽が降り注いでいる村の映像というのは美しいのです。脱穀作業で籾殻が巻き上がる中で、村人全員が作業をする。
疲れれば、みんなで談笑しながら休む。それに対して、都会に移り住んだ村人たちは、冬の曇り空の中にいる。ずっと顰めっ面をしている。
村では常に「物」が不足していて、電球にしてもシェアしなければいけない。
だけど「贈与」で成り立っている村の中というのは、ある種の理想郷のように描かれています。まぁ、もちろん賃金も貰えないで搾取されているのですから、偽りの理想郷なのですけどね。
都会に出てからの彼らは、そもそも「交換」するものを持っていませんから、犯罪に手を染めることになってしまっています野草が食べられることをラザロから教わって、懸命に出荷できる商品に変えようとしている少年の姿が、私は好きでした。
自分のしてきたことが良くないことだと、彼には分かっているのです。
寓意を持って対比される2つの世界において、そのどちらでもラザロは変わらないのです。常に与えようとする。相手の幸福を願っているとか、高尚な理由がある訳でもなく、それしか彼にはないのです。
「交換」というルールで成り立っている資本主義社会。
結局のところ、その社会にラザロの居場所はないのでしょうね。銀行という、まるで資本主義の象徴であるかのような場所で(映画の中の銀行は無機質で、冷たい光沢を放つ場所として撮影されています)
ラザロが亡くなってしまうのは、そうならざるを得なかった物語の「終わり」なのかもしれません。