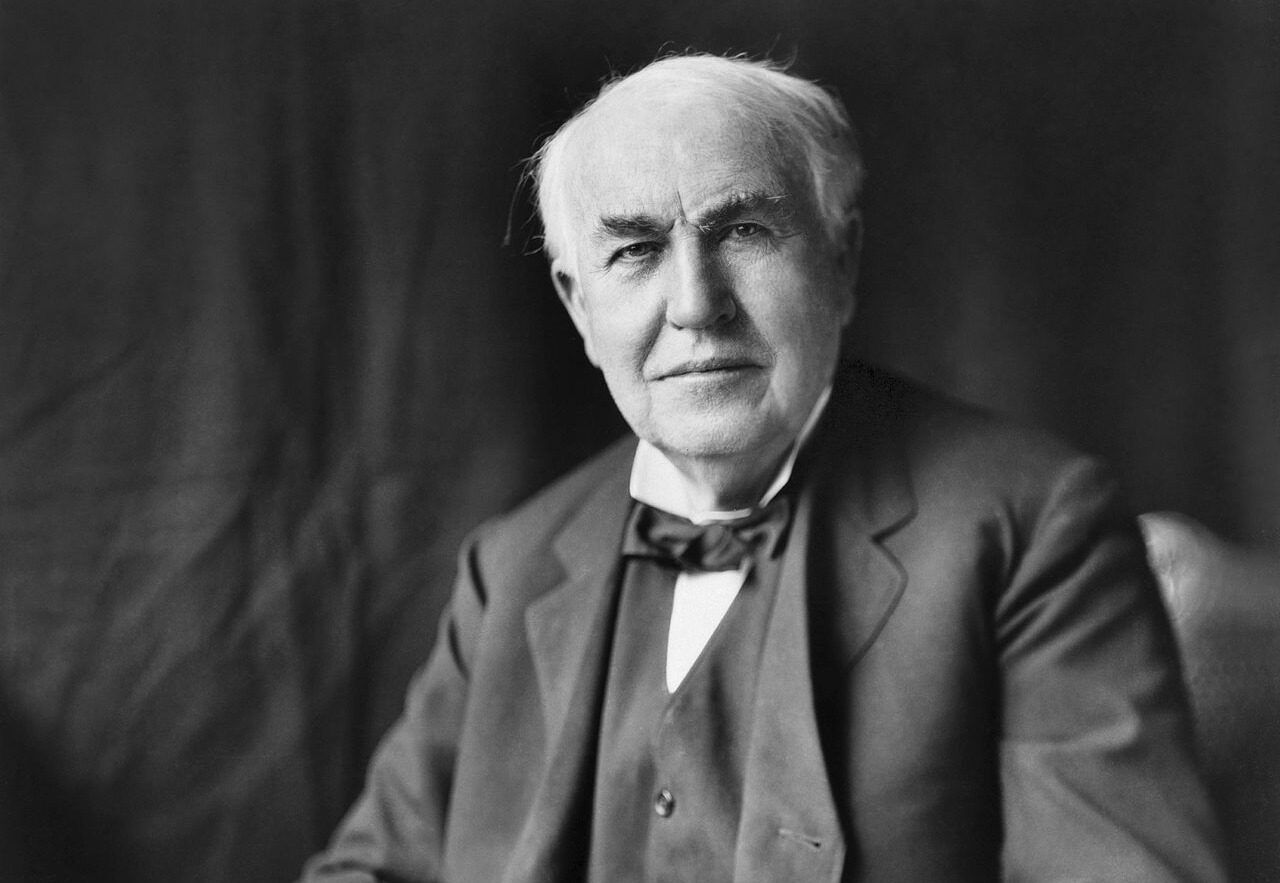記憶というのは不思議なもので、何かを経験して数ヶ月なり数年なりが過ぎた後に、何を記憶しているのかは分からないのですね。記憶の研究で、長期記憶として保存されやすい傾向を持っているのは①その記憶が事実に反していない(つまり、それは現実に起こったことで、妄想や思い違いではないということです)に加えて②その記憶を保持することがその人らしいことであると言われていますけど、②については説明しないと分かりにくいかもしれません。
例えば、大好きなミュージシャンのライブを見るためにどこかの町に行ったとします。そのミュージシャンのファンであることは、その人らしさの一部ですから、ライブの記憶は保持されるでしょう。音楽ファンであると同時に絵画に興味を持っていたら…ライブ前に立ち寄ったカフェのコーヒーの味や、どんなチェアに座ったかは忘れてしまっても、壁にかかっていたロートレックの絵画は覚えているかもしれない。ライブの席の隣の人が身体をゆすって、もしもあなたに触れてしまったら、肉体的に接触されることを好まないタイプの人であれば不快な記憶として保持される(だから、ライブに行くのはやめようと思うかもしれないですね)可能性が高いですけど、そうでなければ会場を出た頃には忘れてしまうかもしれない。
こういう「その人らしさ」…言ってみたら、心理的なホメオスタシスのようなものが、記憶に関係しているというのは興味深いと思います。なぜって…何を覚えているかが、あなたらしさということになるからですね。反対にずいぶん時間が経っているのにも関わらず、何かを覚えている。忘れられない。そういう記憶を紐解けば、自分が分かるということでもあります。PTSDで悩まれている方が、不意に想起される記憶に圧倒されてしまうのは、その記憶が今の自分と深くつながっているからです。
そういう意味で言うと、パリの記憶というのは、どうも私という人間を作っている要素の一つになっているように思うのです。
ニコラ・フィリベールのドキュメンタリー映画をまとめて何本か見たのですけど、ラ・ボルトの精神病院であるとか、パリ国立自然史博物館であるとか、フランスの風景を見ていて、過去にパリ郊外で精神病院の設計に携わったことを思い出しました。
治療の進展度合いに応じて、部屋の色を変化させるとか、かなり手の込んだ仕事をすることになったのですけど、この期間というのは楽しかったのですね。だけど、仕事そのものよりも泊まっていたホテルの窓から見たパリの風景のことばかり思い出すのです。どういう仕事をしたかについては思い出せるのですけど、細部の手触りのようなものは抜け落ちている。それに比べて大きな窓ガラスの向こうに広がっていたパリの風景のことは、はっきりと思い出すことができるのです。
だいたい仕事で海外に行くと(この時はニューヨークで暮らしていましたから、日本に来るのも海外だった訳ですけど)集中して仕事をして、夕食はルーム・サービスということがほとんどでした。
アメリカの味気ないルーム・サービスとは違って、ちゃんと磨かれたカトラリーが運ばれてくるパリのルーム・サービスを気に入って、毎日窓際のテーブルで食事をしながら外をずっと見ていました。
外はかなり冷え込んでいて、暖かな部屋との気温差でガラスが結露している。ぼんやりと滲んだように見えるパリの夜景は美しくて、ベッドに入るまでずっと外を眺めていたこともありました。
仕事に疲れてホテルに戻ってくると、たくさんの窓からぼんやりと光が漏れているのが見える。あの光の1つ1つに宿泊客がいるのだなぁと、当たり前のことなのですけど思いました。私が部屋に戻って電灯をつけると、もう1つ明るい窓が増えるのだと思うと、なんだか嬉しかったのですね。
そんなことを思い出して、寒い夜に暖炉に火を入れて本を読んでいるのが好きだったなと、そのことも思い出したのですね。テキサスだったと思うのですけど、ちょっと長期滞在したホテルの離れのような場所で本ばかり読んでいたのです。
「私は暖かい場所にいて、守られている気がする」
その感覚がきっと好きなのだと思います。
その記憶には私らしさがある。
私の中のもう一人の私である無意識のシステムが、その記憶を残そうと判断した。私はふとした折にそのことを思い出して、ああ、私は私なのだと、当たり前のことを再認識する。
私が私であることの保証は、おそらく連続する記憶の中にしかないのですけど、私が私であることは思い出すたびに強化されていくことになる。思い出したくもない記憶に襲われてしまうPTSDで悩まされている方がどれほど苦しいか。改めてそのことを考えさせられた気がしました。