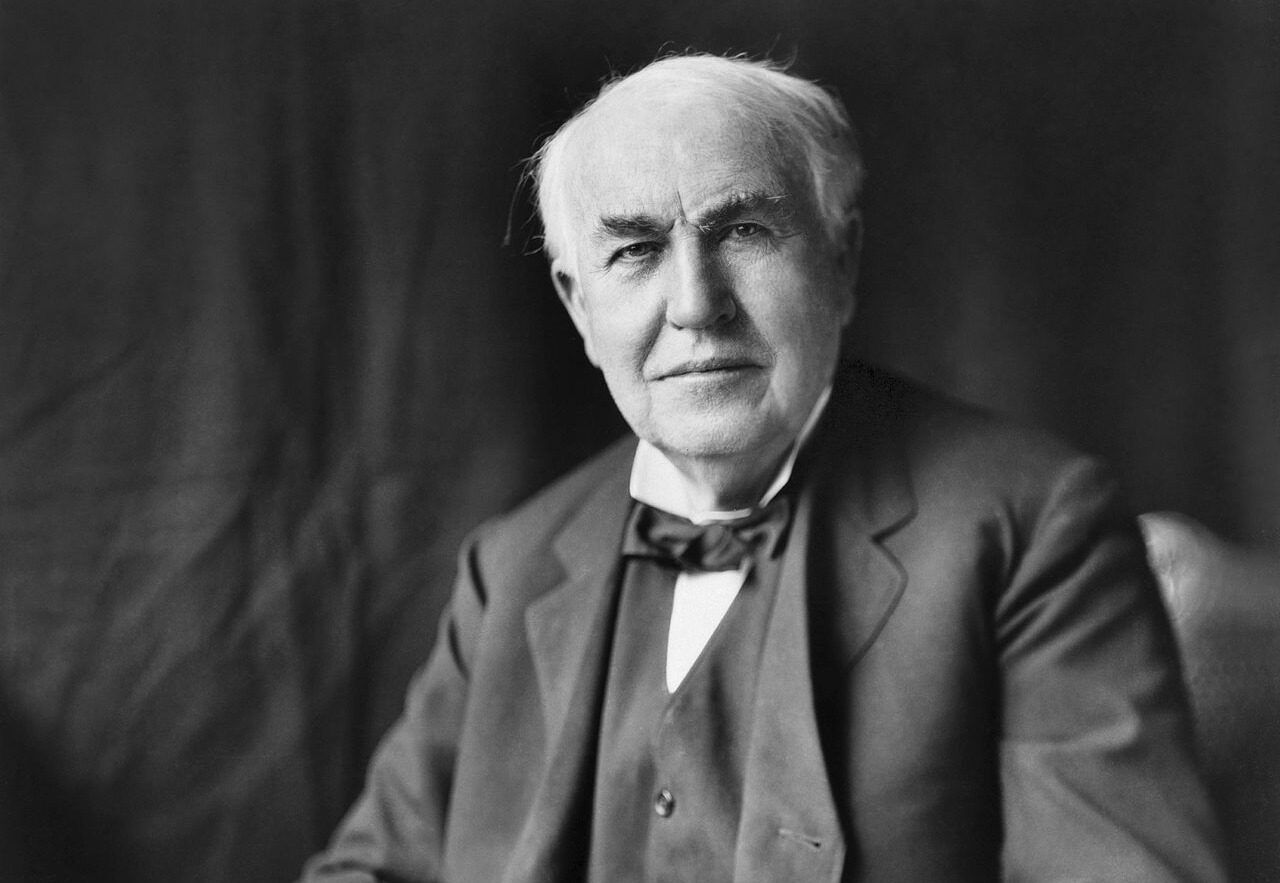「孤独」と聞くと、ネガティブなものとして捉えがちですけどね…哲学者のハンナ・アーレントは「孤独」はとても望ましい状態と捉えていて、そこにネガティブニュアンスはまったく含まれていないのです。そして、「孤独」とは「一人のうちで二人」になっている状態であるとも述べています。
ニュアンスとしては「孤独」を楽しむことができるのが大人。そういう感じなのでしょうね。イギリスでは、公園のベンチで空を見上げていたお年寄りの女性に、寂しそうだったので声をかけたら「私は孤独を楽しんでいるのよ。邪魔をしないで」と言われたなんて話がありますけど(イギリス人気質を表すエピソードとしてよく使われます)アーレントが言おうとしている「孤独」とは、そういう類のものだと思うのです。
それでは、「一人のうちで二人に」なっている状態というのは、どういう状態なのか?
精神科医の斎藤学さんは「寂しい」と感じた時に成熟した人は何をするでしょうか?と『「自分のために生きていける」ということ』で語り始めます。
「まず親しい人のところへ行こうとしたり、呼び出したりしようとします。それが無理なら、親密な人との充実した関係を胸に思い描きます。幸せな自分(の人間関係)をすぐに想い出せることも、大人の条件のひとつなのです。「あの人は何をしているかな?」などと考えて、手紙を書いたりします。もう死んでしまった大昔の人と対話します。昔の人は活字の形で語りかけていますので、読書ということになります。対話しながら読みます。今の世に存在して名を知られていながら、自分とは面識のない人とも読書の形で対話できます。
要するに孤独なときにも、精神的に成熟した人は「他者と共にある」のです。容易に他者を想起できるのです。」
まるでアーレントの言う「一人のうちで二人に」なっている状態を解説してくれているような文章ですけど、全くこの通りだと思うのです。斎藤学さんは、このような「自己との対話」について、あくまでもダイアログ(対話)であるけれど、2人での対話とも違うから1、5人の対話と呼んでいるそうです。
齋藤学さんの他者は、あくまでも自分の外にいる他者ですけど、他者というのであれば、自分自身だって本来は他者なのです。
ランボーは「私とは他者である」と書き残していますし、フロイトも「自我は自分の家の主人ではない」と書いています。アーレントの言っている「一人のうちで二人に」なっている状態というのは、自分の内側に在るもう一人の自分と二人になっている。そう考えることもできるのですね。
哲学的な話であるとか、難解な精神医学の話ではなく、シンプルな事実なのですけど、私たちが「私」と思っているのは、だいたい「あたま」で考えている「私」です。ところが「私」というのは「あたま」だけではなく「こころ」だって存在する訳です。そして「こころ」は5歳くらいの自分だと考えられているのですね。
社会人だから、辛くても会社に行くべきだ。そう主張する「あたま」が、もう休んじゃおうよ。あんなブラック企業なんて辞めちまおうと言ってくる「こころ」を抑圧し続けた結果が「うつ病」の原因。そのように説明されることもありますけど、ここで言う「こころ」とは、フロイトの言うところの無意識なのですね。
つまり「あたま」でばかり考えて「あたま」でっかちの状態になっていると、自分の「こころ」とはつながれなくなってしまう。
だけど、考えてみてください。新しいアイデアや、インスピレーションの源は、たいがい「こころ」の奥からやってくるものなのです。
アーレントは、人間が一人で在る状態について「孤絶(isolation)」と「孤立(loneliness)」と「孤独(solitude)」の3種類があると述べています。
「孤絶」というのは、何かの作業に気を取られてしまっていて、他の人とのみならず自分自身ともつながっていない状態のことです。仕事が忙しくて、誰の言葉も耳に入らない。そういう状態だと説明しています。「孤立」とは「ひとりぼっち」といったイメージですね。よく言われる「ぼっち」という状態です。そして、その状況を苦にしすぎていて、自分自身ともうまくつながれない状態に陥っている。アーレントはそう言うのです。それに対して自分自身とつながっている状態である「孤独」を高く評価している。
「一人のうちで二人に」なっている状態(それを「孤独」と彼女は言います)というのは、自分の中で「あたま」と「こころ」がつながっている状態だと思うのです。