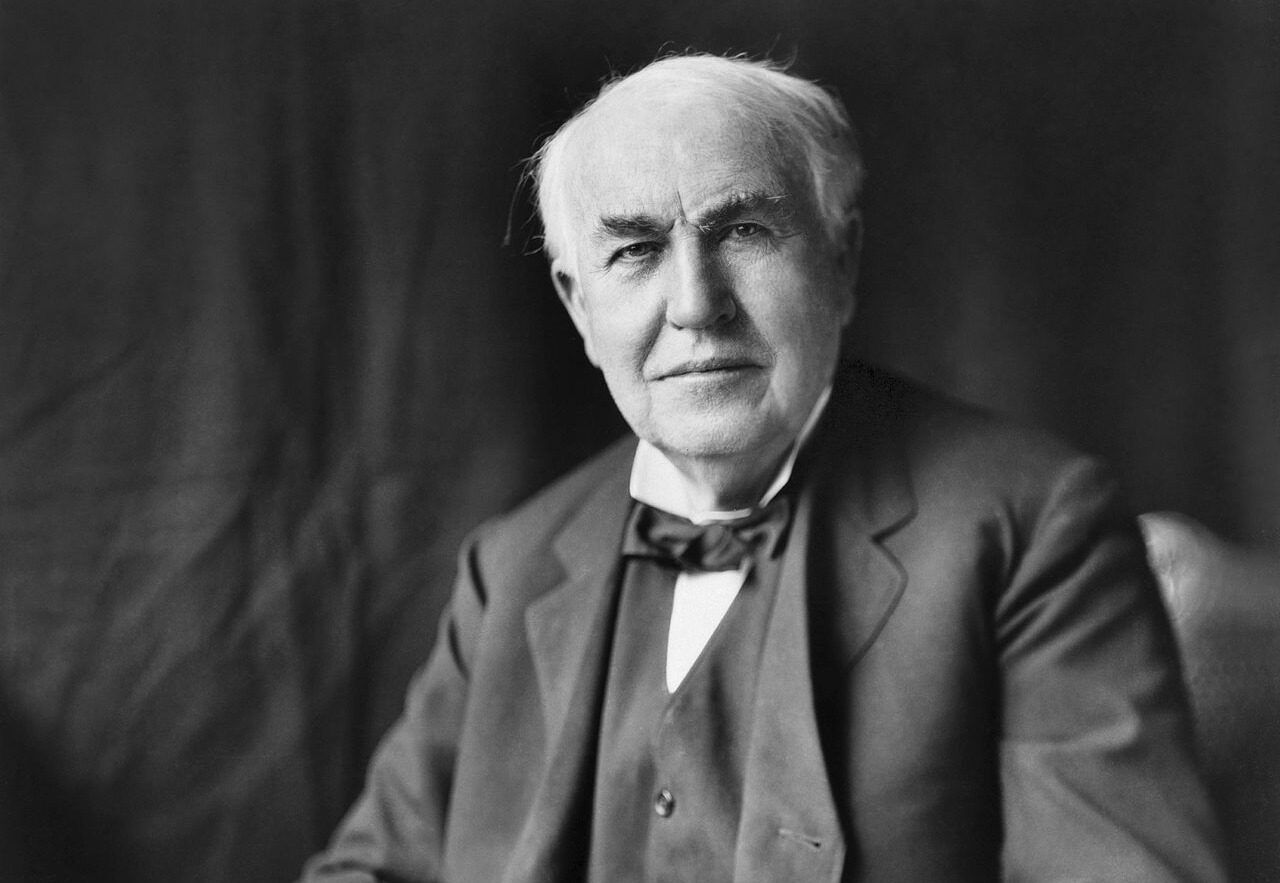ビクトル・エリセの『エル・スール』という映画は、父親の死から主人公の少女が立ち直るところで終わります。父が生まれ育った南(エル・スールというのは南という意味です)に行こうと少女は決意するのですけど…本来であれば、この続きが撮影される予定だったそうです。
プロデューサーの指示だったそうなのですけど、映画では続きが語られることはなくなりました。私は映画の終わり方を気に入っているのですけど、続きがあるといったら…それはまぁ気になりますよね。
日本語に原作小説が翻訳されていることを知ったのは最近のことなのですけど、作者のアデライダ・ガルシア=モラレスさんは、ビクトル・エリセと結婚していたこともあるらしくて、二人の間には息子もいるそうです。
奥さんの書いた原作を、夫が映画化した作品が『エル・スール』ということになるのでしょうけど、原作を読んでみると、映画とはかなり違いがあって、確かに南(具体的にはセヴィリアです)に向かった後が語られるのですけど、小説を映画の続きと考えていいかというと、どうもそれは違うように感じるのです。
というのも、父親に恋人がいたことを娘が知るという物語の骨子は同じでも、その相手というのがずいぶん違うからです。映画の方は女優という設定だった謎の女性は、原作では父の幼馴染になっています。小説には父の恋人だった女性の息子も登場してくるのですけど…主人公の少女に恋してしまう。それは運命的な恋だと彼は感じるのですけど、もしかしたら彼女の弟なのかもしれないのですね。
彼女は結局、もう二度とここへ戻ることはないだろうと決めて…セヴィリアを去ることになるのですけど、原作を映画化していたとしても(おそらく映画でも、父の恋人だった女優の息子と関わることになったでしょう)映画を見終わって心に残る余韻というのは、現実に映画化された『エル・スール』のエンディングと変わらなかったように思うのですね。
結局のところ、原作小説にしろ、映画にしろ、『エル・スール』という作品は、弱い男(亡くなる父親)の周りに配置された強い女たちの物語だと思うのです。
作品中、最も弱い存在として描かれている母親にしても、最終的には過去を振り切って実家に戻るという選択をしますしね。少女の成長物語と解釈できる『エル・スール』ですけど、成長というのは女性としての強さを身につけていくことである。そう描かれているように思うのです。
小説を読み終えて、別の本のことを思い出しました。文化人類学者が、中米でシャーマンの修行が行われている状況を報告したものなのですけど…幻覚性を持つ植物を摂取した後、シャーマンの志願者は山に放置されるのです。実は、師匠のシャーマンが見守っているのですけど、そのことは志願者には知らされていません。
これから3日3晩、おまえはこの山にいることになる。知っての通りこの山にはピューマがいるから、襲われるかもしれない。だから、おまえは自分がピューマになったと信じなければいけない。仲間を襲おうとはピューマは思わないからな。だけど、完全にピューマになってしまったら、もう人間の世界には戻れない。おまえは、ピューマであり、人間であるという状態に自分を置かなければならないのだ。
半死半生で山を降りてくる、新しいシャーマンを出迎えるために、村の女性たちは祝宴の準備をしています。文化人類学者は、その女性にも話を聞いているのですけど、その女性の言葉がなかなかに興味深いのです。
男というのは、あそこまでしないと分からないんだね。死んでしまう寸前までいかないと分からないんだろう。だけどね、女ってのは、男がそうやって知ることを、そもそも生まれた時から知っているんだよ。
亡くなる寸前に父は娘に言います。「いいかい。一番性質が悪い苦しみというのは、これといった理由がないやつなんだ。あらゆることが原因になっていて、とくに何かがあるわけじゃない。まるで顔がないみたいなのさ」
「どうして?物事には必ず理由があって、それについて話せるはずよ」父の言葉に娘はそう答えるのですけど、きっと娘は感覚で知っているのです。シャーマンを迎える村の女性のように。
女性性というのは、本来そういうものなのかもしれません。