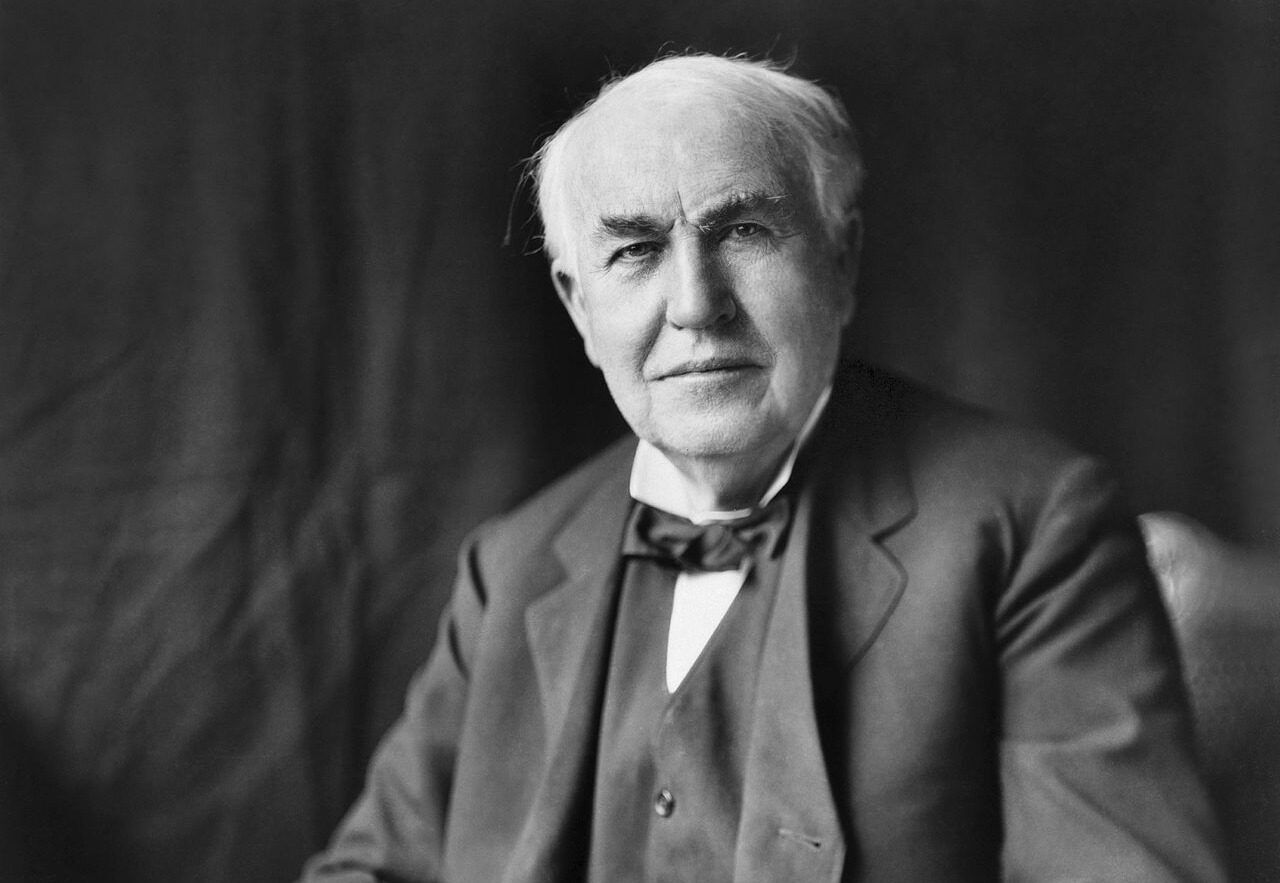彼女は音楽に関わる仕事をしていましたから、お酒を飲みながら話す内容も、音楽関連の話が多かったのですね。
あれはいつのことだったか…たぶんエラ・フィッツジェラルドとか、彼女が愛していたシンガーの話をしていた時だったと思います。
人から聞いた話なんだけどね。彼女は言いました。人は死んでも、すぐには消えてなくなったりはしない。
こういう話というのは、熟練のバーテンダーのように、軽く相槌をうちながら相手が話すままにしておくのが望ましいのですよね。
普段の私からしたら、ちょっと帰宅時間が遅いなと思うくらいの深夜。静かでほとんど客のいないテラス。目の前の道路を走る車もほとんどなくなって、時折流しのタクシーが通るくらい。テーブルには飲みかけのワイン。食べ残したフィッシュ&チップスは冷めてしまっている。ラストオーダーを知らせに来たウェイターは行ってしまったから、しばらくは誰も話しかけてこない。
こういう状況でなければ、おそらく口にされなかった話題。間違っても、真夏のビーチサイドでピニャ・コラーダを飲みながら話す話ではない。状況の条件が揃ったからこそ、彼女の心のどこかにある、蔦の絡まった門がそっと開いた。そう言うとカフカの小説みたいですけど。
たとえ精神科医だったとしても(まぁ、私は現実に精神科医なのですけどね)口を挟むことができない。そういう話を彼女は語ろうとしている。