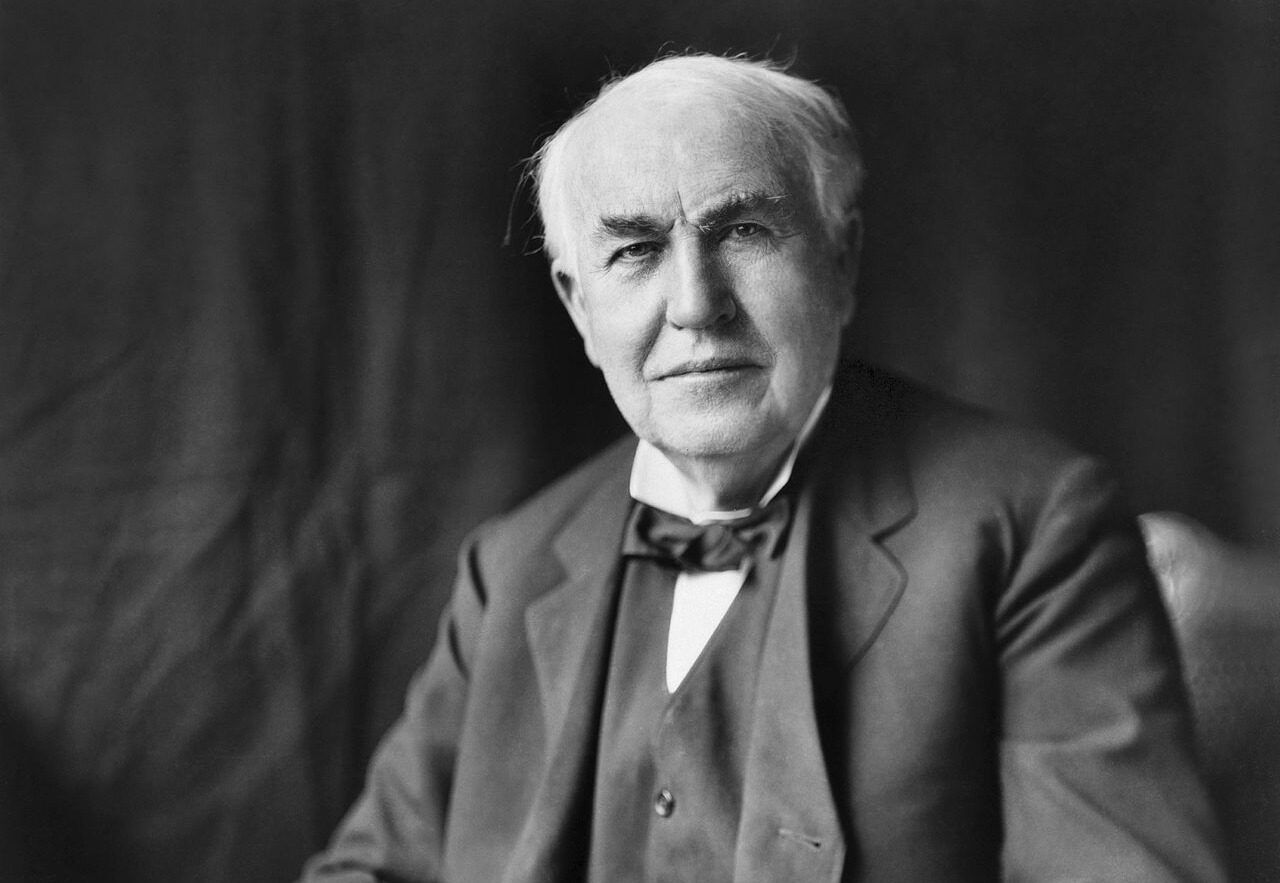『アダマン号に乗って』でベルリン映画祭で金熊賞を獲ったニコラ・フィリベール監督のドキュメンタリー映画を数本見たのですけど、中でも『すべての些細な事柄』という映画には職業柄たくさんのことを考えさせられました。
映画の舞台となっているのはロワール地方にあるラ・ボルド病院なのですけど、『アンチ・オイディプス』などで知られているフェリックス・ガタリが診療の責任者だったことで有名な精神病院です。共著者だったジル・ドゥルーズは、何度も誘われたにも関わらず頑としてラ・ボルドには来なかったことでも有名ですけどね。
1951年にラカン派の精神分析医のジャン・ウリによって開設されたラ・ボルド病院ですけど、映画の冒頭に俯瞰撮影で目に入ってくるのは…城(キャッスルではなく、小規模なシャトーに当たるでしょうけど)のような建物なのですね。よくある精神病院の無機質な建物とは明らかに違うし、建物の周りには広大な庭園が広がっている。
そこでは「患者が働き、自分の創造性を発揮できるような状況を生み出して、彼らに率先して参加し、責任を与えるようにしようとしたのである」とWikipediaには書かれていますけど、映画の中でも、白衣やそれに類する服を着ていない医師や看護師と一緒になって食事をしている患者を見ていると…誰が患者なのかはぱっと見では分からないくらいなのですね。
毎年夏に、患者たちと病院スタッフが一緒に世界の古典的な作品の中から選んで演じるお芝居がラ・ボルド病院の名物なのですけど、ヴィトルド・ゴンブローヴィッチの「オペレッタ」をお芝居として作っていく様子をカメラで追ったものが『すべての些細な事柄』なのです。
統合失調症の患者たちですから、それはまぁすんなりと舞台稽古が進んでいく訳ではありませんし、いろいろとトラブルだって起こる。だけど、患者の家族や募集された観客たちの前で演じられる舞台は成功するのです。そしてまた、病院には静かな日常が戻ってきます。
写真家のナン・ゴールディンが、友人カップルを撮影するときに、何日も泊まり込んで…カメラを向けても緊張しない、不自然にならないようにカメラに慣れてもらうことをしたと語っているのを読んだことがありますけど、おそらくニコラ・フィリベールも同じようにラ・ボルトに長期間滞在したのだと思います。患者たちの様子というのが、すごく自然体だからです。ああ、また撮っているのね。患者の一人がそう呟く。そういう感じで映画は進んでいくのですけど、被写体に対する距離の取り方というのが私は好きでした。
これほどの施設を使って、食事も病院内で手作りされているとか、庭園が常に美しく管理されているのを見ていると…きっと費用も高くて、富裕層の家族でないと入院できないだろうなと思っていたのですけど、ラ・ボルドに滞在して写真を撮った田村尚子さんによると、パリの精神病院よりもむしろ入院費用は安いのだそうです。日本で言うところの第三セクター方式で運営されているようですね。
写真集『ソローニュの森』が刊行された際のインタビューで彼女が語っていることも、彼女の写真も大好きなのですけど、ちょっとご紹介しますね。
「ウリ先生は、「社会的に疎外された患者が、精神病院で、さらに精神的に疎外されてはならない。精神的に疎外された患者が、さらには社会的に疎外されてはいけない」といったことをおっしゃっていますから、病院の雰囲気を含めて、ひとつひとつのことから発するすべてが大事なんです。建物とかも、言ってみれば結構古めかしいですが、それがまたいいんですね。ただ単にフォトジェニックだという意味ではなく、人を疎外しないという意味においても。それでも、国や自治体の検査が入ると、それに通るようにきれいにしなくてはいけないわけですが、そのときも、できるだけみんなで自発的にきれいにするよう、それとなく患者さんたちに促していくというアプローチが取られるんです。」
彼女は6年で6回ラ・ボルドに滞在したそうですけど、最初は逃げ出したこともあったそうです。彼女の写真には統合失調症の方に特徴的な強い視線をカメラに向けている方も多いですから、医学的なトレーニングを受けていない彼女にはきつかったようです。だけど、少しずつ患者との丁度いい距離感をつかんでいき、写真が撮れるようになったのだと思うのですね。
患者やスタッフで自転車で小旅行に出かけた写真。強い光でハレーションを起こしたような画面には、彼らの後ろ姿が写っています。患者を閉じ込めるのではなく、世界と関わることで治していく。ラ・ボルト精神病院のような場所がこの世界に存在するのは…人間という存在の善き部分の顕れのように思います。
写真: NYメンタルケアサロン
カウンセリングルーム